トピックス Topics
2020年4月25日ニュース
ファミリービジネス関連の書籍を紹介する「J.P.通信」でEps.13 一志 治夫著『アンデルセン物語 食卓に志を運ぶ「パン屋」の誇り』を投稿しました。
(FBページはこちら⇒ https://www.facebook.com/JP通信-by-FEMO-782507828813683/?modal=admin_todo_tour)
国内の1日あたりの感染者数がついに200人を超えました。終わりの見えない自宅待機要請が、日々私たちの生活における豊かさを失わせている気がします。そんな中だからこそ、1人の勝手な行動が、本来安全であるはずの場所を一気に危険地帯にさせてしまう恐れがあるのです。今こそ、私たち一人一人の危機意識と考える力が問われているのではないかと感じています。今回は、そんな今を必死に戦う人たちに勇気を与えてくれる、ある経営者夫婦の物語です。
今回ご紹介するのは、美味しいパンの代名詞ともいえる企業「アンデルセン」。社名はデンマークの童話作家の名に由来しています。「彼が童話によって世界の人々の心を豊かにしたように、食によって、人々に幸せを運びたい」という思いを込めて名付けられました。今や誰もが知る有名企業ですが、広島がその誕生の地だというのはご存知でしょうか。
創業者である高木俊介・彬子夫妻は、戦後間もない焼け野原になった広島で、1948年にアンデルセンの前身となる「タカキのパン」をオープンさせました。夫婦であり、同志でもあった高木夫妻は、常に先を見越した経営戦略と哲学をもって挑戦を続け、敗戦のどん底から今のアンデルセンという自分たちのブランドを築き上げました。
この本の中で著者である一志治夫さんは、夫妻の言葉を、読者に一言添えた上でそのまま引用している部分が多々あります。彼らの言葉1つ1つを、そのまま伝えることにこそ意味があると考えてのものだったように、私には感じられました。
あえて「しんどい道」を選ぶことに意味があると信じ、常に切磋琢磨してきたアンデルセンの精神。今を生きる私たちのこれからを考える上で、背中を押してくれる言葉の数々が詰まっています。是非、ご一読下さい。
J.P.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『アンデルセン物語 食卓に志を運ぶ「パン屋」の誇り』
一志 治夫 著
「暮らしにヒュッゲ」。これは1988年、アンデルセン改装の際に掲げられたスローガンである。ヒュッゲはデンマーク語で、「人と人とのふれあいから生まれる、温かな居心地のよい雰囲気」を意味する。彼らは単なるパン屋にとどまらず、パンが生活習慣に定着した生活そのものを売ることに自分たち企業の存在意義を感じていた。生活様式そのものを提案し、その生活に必要なものを供給していくという、いわゆる「ライフスタイル・マーチャンダイジング」である。その壮大な目的達成のための道は、当然厳しく難しいものだったが、自分たちの信念を貫いた高木夫妻の戦いの日々から私たちが学ぶべきものは多い。
彼らの戦いは、終戦直後の広島というどん底から始まった。終戦直後の食糧事情は本当に悲惨だった。今考えれば到底食べられたものではない代用食を、皆飢えを凌ぐために自分たちの衣料を金に換えて求めたのだ。加えて、ヤミで流れる食糧が無ければ国民は生きていけなかった。警察ですら目をつぶっていたような時代だ。高木夫妻も例に漏れず、代用食の団子を売って生活していたが、俊介はそんな時代がそう長くは続かないと予感していた。「人は美味しいものを食べれば、もっと美味しいものを、となっていく。少しずつ贅沢になり、代用食のようなものは必ず売れなくなるに決まっている」と。その予感は的中した。別の商売を始めようと決意した。
「人は誰でも具体的にはよく分からないが、今日よりもとにかく少しでも精神的にも、物質的にも向上したいという幻のような考えがある。それを1つ1つ掘り出していくのが、企業・我々の仕事ではないか」。それが俊介の考え方だった。何よりも俊介のパンへの情熱が、アンデルセンの前身である「タカキのパン」創業の大きな原動力だった。彼は戦時中、シンガポール抑留時代に食べた山型のイギリスパンの味が忘れられなかった。そんなパンを自分たちで作って、自信あるパンとしてお客様に売ろうと身を粉にして働いた。多忙な中で自然と、夫が「経営」し、妻が「広報宣伝ならびに教育」という役割分担が出来ていったのかもしれない。夫である俊介は、常に先を見通した経営戦略で手腕を発揮しつつ、欧米視察を通して、自分たちが日本で作るべきパンを開拓し続けた。新たな技術習得にも意欲的で、経営の中枢を成す部下を実の子供のように育てた。
一方で店を切り盛りしていく中で、妻である彬子は商売にとって大切な感覚や勘を磨いた。お客様の動き、買い方の変化や顔色を敏感に見て取ることで、「良心に恥じない商売」をすることの重要性を叩き込まれた。これが後に、彬子の活動に大きく影響してくることになる。
1954年に日本で初めて豊作が訪れ、コメの値段が下がったことにより、彼らはよりクオリティーを重視したパン作りを確立していくことになった。1972年にパンの冷凍技術で広範な特許を取得し、日本初のパンのセルフ方式を採用。さらに新聞を使った「朝食キャンペーン」広告で朝食の重要性を説くなど、パン屋にとどまらない活動を次々に打ち出していく。
そしてついに1978年、地上8階地下1階建ての「広島アンデルセン」が落成(現在は改装工事中)。広島のランドマークになるアンデルセンが完成した。
しかしそんな輝かしい成功とは別に、アンデルセンの本当の価値は、時代が変わっても揺らぐことのない経営理念、すなわち先に述べた「良心に恥じない商売」にある。物が豊かなことが当たり前の現代社会において、世の中は類似品が氾濫し、商品の魅力がどんどん曖昧になっている。つまり、商品の個性化や差別化では、問題の根本的解決はできないということだ。となれば生活者・消費者の意識は、自ずと企業そのものの考え方や姿勢に向く。だからこそ、今一度企業の存在意義や役割を再認識しなければいけないという危機意識が欠かせない。人間教育に人一倍金も労力もかけてきた彬子は、そう指摘する。
彬子の人間教育に懸ける並々ならぬ情熱には、終戦直後からずっと抱えていたひっかかりが関係している。それは「パン屋」と呼び捨てにされた、かつて自分たちの仕事が尊ばれることのなかった環境への悔しさだった。当時は「牛乳屋さん」よりも、パン屋は下に見られていたのだ。そんな環境で働いて、何の幸せがあるのかと。だからこそ彬子は、入社した社員たちをはじめ教育に投資を惜しまなかった。海外留学も説教的に行い、自分たちのパンを「なくてはならないもの」にするため、目先の利益に囚われることなく、最初は売れない商品でも売れるまで根気強く待った。現場の幹部や責任者から何と言われても、「お客様に迷惑をかけていないのなら、1年間は目をつむってほしい」とハッキリと主張した。育てたものをどう生かし、どう動かすかというグランドデザインがそこにはあった。
先に述べた「良心に恥じない商売」とはすなわち、「全ての人たちが一段上を目指して、お互いが磨きをかけながらやっていく」、というものだ。良心があればそれに照らして自分の判断で行動することが出来る。訓練することで、「思う」人からもう一歩先の「考える」人へと成長することで、はじめて仕事は定着するのだと、彬子は自身の経験からそう学んでいる。
著者である一志氏曰く、彬子は自身の信念についてこう語っている。
「目先の数字ばかり追うのではなく、育てるべきものを本気になって売ることこそが、最終的には利益を生む。お客様のニーズに合わせるのではなく、一歩進んだものを先んじて提供し、アンデルセンのものは美味しいという信頼を持って下さるお客様をどう増やしていくか。それこそが商いなのではないか。その哲学を崩さない限り、取り扱い販売する人にも、アンデルセンのパンを売っていてよかったと思っていただける。社員も、お客様も、売っている店も、皆が誇りを持てる。そんなパンを作り続けるべきだ」。
人は、死ぬその寸前まで成長を止めない。アンデルセン創業のストーリーには、そんな人間の底知れない進化へのエネルギーを感じる。そして、自分を信じて今を生きることの大切さも。いつか自分の信じたものが、目の前に形を成して表われるその時まで、私たちも自分の心に恥じない生き方をしていきたいものだ。

お問い合わせ Inquiry
-
-

お電話:
03-6822-6840
-
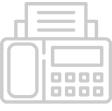
FAX:
03-6822-6850
営業時間:月~金 9:00~18:00
-
-
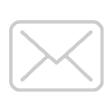
メールでのお問い合わせ
